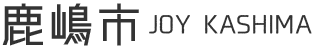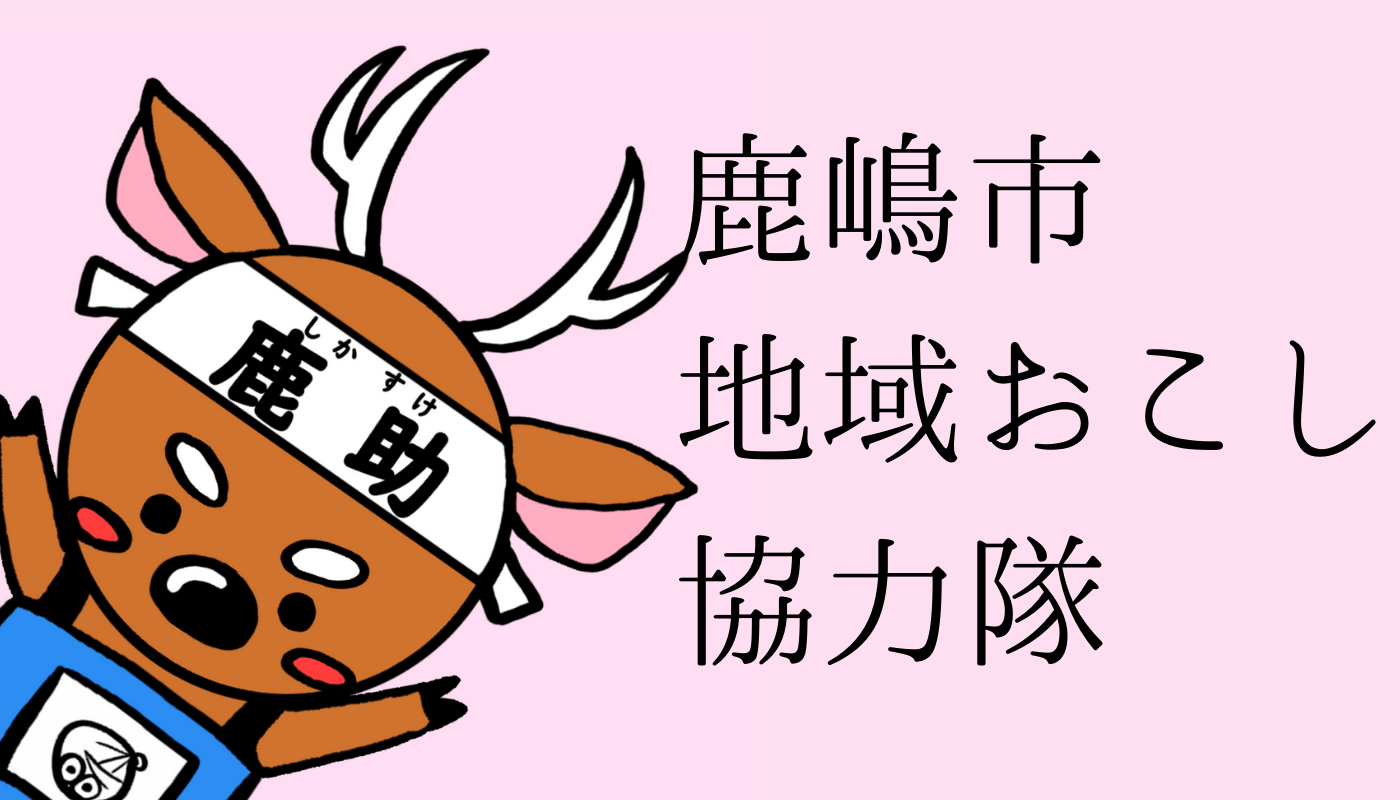※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
国民年金保険料の免除について
国民年金保険料は被保険者「本人」とその「配偶者」、被保険者が属する世帯の「世帯主」の三者の前年の所得を基に免除判定をし、該当すれば「全額免除」または「一部免除」等を受けることができます。これには本人(または代理人)からの申請が必要です。
免除決定した期間は年金受給資格を判定する120月(年金受給権が発生する月数)に換算することができますが、免除申請をせず保険料を未納にしていた期間は月数として換算されません。また、免除申請をしていても「一部免除」の場合、残りの支払うべき保険料を納めないと「未納」として扱われますのでご注意ください。
| 免除種類 |
被保険者 負担額 |
所得基準 |
年金受給時の 満額からの減額 |
特例併用 |
|---|---|---|---|---|
|
全額免除 (法定免除) |
0円 | 67万円以下 | 半分減額 | 可 |
| 4分の1免除 | 13,130円 | 168万円以下 | 8分の1減額 | 可 |
| 半額免除 | 8,760円 | 128万円以下 | 8分の2減額 | 可 |
| 4分の3免除 | 4,380円 | 88万円以下 | 8分の3減額 | 可 |
| 納付猶予 | 0円 |
67万円以下 (本人かつ配偶者) |
全部減額 | 可 |
| 学生納付特例 | 0円 | 128万円以下 | 全部減額 | 可 |
| 産前産後免除 | 0円 | なし | 減額なし | × |
※扶養親族数により所得基準額が変更になります。
※法定免除は生活保護期間中、障害年金受給期間中であれば再度の申請の必要はなく、扱いは全額免除と同様です。
※全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例は申請月より2年1ヶ月前まで遡って申請することができます。
※免除した期間の保険料は、10年以内であれば申請により納めることも可能です。
失業等による特例免除について
失業(退職)・倒産・事業の廃止などの事実が確認できる書類を添付していただくと、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
| 添付書類 | 書類の発行元 | |
|---|---|---|
|
雇用保険 加入者 |
雇用保険 被保険者離職票(写し) | 退職した勤務先 |
| 雇用保険 被保険者資格喪失確認通知書(写し) | 退職した勤務先 | |
| 雇用保険 受給資格者証(写し) | ハローワーク | |
| 雇用保険 被保険者資格取得届出確認照会回答書 | ハローワーク(申請必要) | |
| 雇用保険未加入者 | 退職証明書(写し)※住民税の取扱明記が必要 | 退職した勤務先 |
|
退職証明書(写し)+住民税変更通知書または納税通知書(写し) ※在職中に給与から住民税天引きされていた場合 |
退職した勤務先/市区町村 | |
| 退職証明書(写し)+退職時の給与明細または離職前後の納税通知書/領収書(写し)※在職中にご自身で住民税を納めていた場合 | 退職した勤務先/市区町村 | |
| 離職証明書(様式あり) | 退職した勤務先にて証明 | |
|
官公庁 退職者 |
退職辞令(写し) | 退職した勤務先 |
| 退職証明書等(写し)※離職日記載のものに限る | 退職した勤務先 | |
| 事業主 | 履歴事項全部証明書※事業の廃止日または解散日が確認できるもの | |
| 閉鎖事項全部証明書 | ||
|
異動届出書(写し)※異動事項が破産の場合は除く 個人事業の開廃業等届出書(写し) 事業廃止届出書(写し) のどれか |
税務署等へ提出した書類 | |
| 廃止届出書(控)または廃止届証明書 | 保健所へ提出した書類(受付印必要) | |
| 総合支援資金貸付決定通知書および申請時の添付書類(写し) |
「全額免除」「一部免除」「納付猶予」の申請について
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・年金手帳、基礎年金番号通知書など年金番号がわかるもの
・委任状(別世帯の方がお手続きされる場合)
※失業(退職)等による場合の申請は別途添付書類が必要です。
(→失業等による特例免除についてを参照)
「学生納付特例」の申請について
申請に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・学生証のコピー(入学日、発行日、有効期限の記載ある面)または在学証明書の原本
(学生証の写真を印刷したものは認められません。また、有効期限の切れた学生証も認められませんのでご注意ください。)
・年金手帳、基礎年金番号通知書など年金番号がわかるもの
・委任状(別世帯の方がお手続きされる場合)
※失業等による特例免除の併用が可能です。所得基準を超えていて、特例免除に該当する場合は、別途添付書類もお持ちください。(→失業等による特例免除についてを参照)
申請後の対応について
学生納付特例は、1度申請すると卒業年度までターンアラウンドのハガキがご自宅に届き、そちらに記入の上ご返送いただくと、申請が継続される仕組みとなっております。ただし、初回の申請を1~3月ごろに行った方や、初回申請時と学校が変わった方、卒業後さらに進学した方等にはハガキは届かず、再度窓口や郵送でのお手続きが必要となりますのでご注意ください。
申請方法について
・窓口
市役所(国保年金課)または大野出張所
・郵送
市役所(国保年金課)
・電子
日本年金機構でマイナポータルを利用した電子申請を行っています。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>をご確認ください。